故人(被相続人)が亡くなった当時、もし出生すれば法定相続人となる資格を有する胎児がいた場合(例えば、故人の子である場合)、その子が後に無事に出生したときは、その子も相続人となる、という考え方が実務上一般的です。(民法886条、大判昭和7年10月6日民集11巻2023頁、停止条件説)。
これは、その子が胎児の段階では相続人ではないものの、後に出生した場合(=死産でない場合)、その子は故人が亡くなった時点に遡って相続人となる、という意味です。
したがって、胎児の段階では未だ相続人ではないため、親や他の者が代理するなどして、胎児を遺産分割協議に参加させることはできません。
また、胎児が出生する前に遺産分割を行ったとしても、その子が出生した時点で、当該遺産分割は無効となります(遺産分割協議書は相続人全員の署名・押印がなければ無効とされるためです(民法907条))。
よって、胎児がいる場合、遺産分割協議はその子が出生するまで保留にしておく必要があります。
投稿者プロフィール

- 代表弁護士
-
新宿を拠点として、相続案件に多数取り組んでいます。
他士業と連携し、スムーズな解決に尽力いたします。
最新の投稿
 記事2023年12月27日寄与分とは?-寄与分の分類や貰えるためのポイントなど詳しく解説します。
記事2023年12月27日寄与分とは?-寄与分の分類や貰えるためのポイントなど詳しく解説します。 記事2023年8月4日代襲相続とは?‐発生する条件や代襲相続人の範囲、割合など詳しく解説します。
記事2023年8月4日代襲相続とは?‐発生する条件や代襲相続人の範囲、割合など詳しく解説します。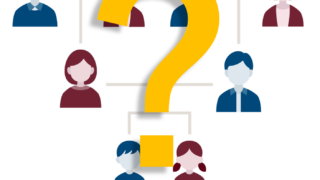 記事2023年8月4日法定相続人とは?相続人の順位と割合をわかりやすく解説します!
記事2023年8月4日法定相続人とは?相続人の順位と割合をわかりやすく解説します! 記事2023年7月10日遺留分とは?‐遺留分をもらえる人や計算方法など、わかりやすく解説します
記事2023年7月10日遺留分とは?‐遺留分をもらえる人や計算方法など、わかりやすく解説します
