当サイト・記事の内容・テキスト・画像等の著作権は、当事務所に帰属します。
無断転載・無断使用はおやめください。
(4)(3)のような節税対策について、従前の裁判例・裁決例において例外ルールが適用された事例―相続税対策(節税策)のみを目的としたと評価されるような場合
ウ 本判決の事案及び判決理由から見る本判決の考え方~より柔軟な判断
1 本判決(最判令和4年4月19日判決)の概要
昨日、相続税等の節税に関する重要な最高裁判決(最判令和4年4月19日判決)が下されました。
判決の概要としては、都心部の不動産における時価(市場における取引価格)と路線価・固定資産税評価額(以下、「路線価等」と略します。)の差額を利用した不動産の相続税対策(節税策)について、「(路線価等によって評価することが)著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」旨、定める財産評価基本通達6項(総則6項)という例外ルールの適用を認め、そのような相続税対策(節税策)を否定する内容です。
1審(東京地裁判決令和元年8月28日金判1583号40頁)・2審(東京高裁判決令和2年6月24日金判1600号36頁)の判決も同様の判断をしていたため、最高裁判決がこれを是認した形となります。
従前の裁判例において、このような例外ルールが適用された事案は、故人(被相続人)が他界する(相続開始する)直前に不動産を購入し相続開始直後に売却したケース(東京高裁平成5年1月16日税資194号75頁)、故人(被相続人)の健康状態が重篤化し他界(相続開始)直前に動産を購入したケース(東京地裁判決令和2年11月12日)など、専ら相続税対策(節税策)のみを目的として不動産購入がなされていたような極端な事案でした。
そのような中、本判決は、不動産の購入時期やその後の経過に照らし、相続税対策(節税策)をも目的としていたことは間違いないが、これのみを目的としていたとまでは必ずしも言えない事案において、例外ルールの適用を認めた点が注目点と考えられます。以下では、このことに関し、本判決の事実関係や経緯について説明の上(=2)、本判決の内容・本判決が、相続税対策(節税策)に与える影響について説明します(=3)。
2 本判決の事実関係及び経緯
(1)時系列順
①平成21年1月:8億3700万円で甲不動産を購入。
その際、代金額支払いのため、6億3000万円を銀行より借り入れた。
②平成21年12月:5億5000万円で乙不動産を購入。
その際、代金額支払いのため、3億7800万円を銀行より借り入れた。
③平成24年6月:故人(被相続人)が94歳で死去した。
④平成25年3月:平成24年時の甲不動産の路線価等に基づく評価額(以下、「路線価等」と略します)が2億4万1474円、乙不動産の路線価等が1億3366万4767円であったことから、共同相続人(納税者)は、かかる路線価等を基準の上、相続税を0円として相続税申告を行った。
具体的には、甲不動産及び乙不動産について路線価等を基準とした上で、積極財産の総額(プラスの財産)を算出したところ、10億156万円となった。
これに対して、消極財産(マイナスの財産)の総額は、上記①及び②の借入れを含む9億9706万円であった。
したがって、課税価格は、10億156万円余―9億9706万円余=2826万1000円となり、そこから、基礎控除をした結果、相続税額は0となった。
⑤平成25年3月:甲不動産は、これを相続した相続人X3により、5億1500万円で売却された。
⑥平成28年3月~4月:そうしたところ、国税庁長官の指示に基づき課税庁は、甲不動産及び乙不動産について財産評価基本通達6項(総則6項)の適用を認め、鑑定評価(収益還元法による時価算定)を行った結果、甲不動産を7億5400万円、乙不動産を5億1900万円として相続税を評価すべき旨の更正処分がなされ、これに基づき共同相続人(納税者)のうち、X1に対し223万円、X2に対し541万円、X3に対し2億7924万円の相続税の課税処分がなされた。
また、過少申告加算税として、X1に30万円、X2に78万円、X3に4186万円の課税処分がなされた。
共同相続人(納税者)は、これを不服として更正処分の取消を求め審査請求を行ったが、国税不服審判所長は、棄却する旨の裁決を行った(平成29年5月23日裁決)。
⑦そこで、共同相続人(納税者)は、これらの課税処分等の取消しを求め、訴訟提起した。
⑧1審(東京地裁判決令和元年8月28日金判1583号40頁)・2審(東京高裁判決令和2年6月24日金判1600号36頁)ともに、財産評価基本通達6項(総則6項)の適用を認め、路線価等とは異なる額に基づきなされた課税処分等に違法ないとした。
共同相続人(納税者)は上告し、最高裁判所によって判断がなされた。
(2)表
(1)で説明した事実関係・経緯を踏まえ、甲不動産及び乙不動産の購入額・借入額、相続開始時点・売却の有無・売却額、路線価等(申告額)、時価(更正処分の基準額)等を表にまとめると以下のようになります。
| 甲不動産 | 乙不動産 | |
| 購入額 (うち借入額) | 8億3700万円 (21年1月) | 5億5000万円 (21年12月) |
| 相続開始時点 | 平成24年6月 | 平成24年6月 |
| 売却の有無・売却額(売却時期) | 無 | 有・5億1500万円 (25年3月) |
| 路線価等・申告額 (申告時期) | 2億4万1474円 (25年3月) | 1億3366万4767円 (25年3月) |
| 時価・更正処分の基準額 (更正処分等の時期) | 7億5400万円 (28年4月) | 5億1900万円 (28年4月) |
3 本判決の内容・本判決が相続税対策(節税策)に与える影響
以下では、まず本判決の結論を述べた上で(=(1))、前提として、相続税評価の算定における原則と例外ルールについて説明します(=(2))。
本判決においても用いられていた、例外ルールを利用した相続税対策(節税策)について説明します。(=(3))
その上で、従前の裁判例・裁決例において例外ルールが適用された事例について説明します(=(4))。
そして、本判決の事案及び判決理由に照らし本判決の考え方が、上記従前の裁判例・裁決例と比較して、例外ルールの適用をより柔軟に認めていることを説明します。(=(5))
最後に、本判決が相続税対策(節税策)に与える影響について述べます。(=(6))
(1)本判決の結論:
前述の通り、本判決は、1審(東京地裁判決令和元年8月28日金判1583号40頁)・2審(東京高裁判決令和2年6月24日金判1600号36頁)と同様に、財産評価基本通達6項(総則6項)の適用を認め、甲不動産及び乙不動産の相続税評価額を、路線価ではなく不動産鑑定に基づく時価とした上で行った課税処分等を適法としました。
この判決は、敗訴した共同相続人(納税者)からみれば、相続税対策(節税策)が否定されてしまったことを意味します。
(2)相続税評価額の算定における原則と例外ルール
ア 原則ルール
相続税算定の基礎となる相続不動産の額は、「時価」によるとされています(相続税法22条)が、一々時価を鑑定していては費用や時間の面でコストがかかりすぎます。
そこで、「時価」とは、国税庁が定める財産評価通達によって算定されるものとし(財産評価通達1条(総則1項))、土地(宅地)に関しては路線価によるものとされ(財産評価基本通達11項)、建物(家屋)に関しては固定資産税評価額によるものとされています(財産評価基本通達89項)。
このように、相続税算定の基礎となる相続不動産の額の算定は、国税庁の定める通達によるのが原則です。
イ 例外ルール
しかし、上記の原則には例外があります。
すなわち、財産評価基本通達には、「通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」という規定が存在しており(財産評価基本通達6項(総則6項))、かかる通達は、裁判例上(最判平成5年10月28日税資199号670号)も、「評価通達によらないことが相当と認められるような特別の事情のある場合には、他の合理的な時価の評価方式によることが許されるもの」として是認されています。
(3)原則ルールを利用した相続税対策(節税策)
(※以下の(3)で説明する相続税対策(節税策)は、あくまで説明の便宜のために紹介しているにすぎず、今回の最高裁判決でも否定されていますので、推奨するものでは決してありません。この点ご留意の上お読み下さい)
前述の通り、相続税の算定に関しては、土地(宅地)については路線価、建物(家屋)については固定資産税評価額を基準とするが、都心部においては、時価(取引価格)が、これらの路線価等よりもかなり上回っているケースが散見されます。
したがって、時価(取引価格)が路線価等より大幅に高い都心部の一等地の不動産であれば、(原則ルールによる限りは、)大幅な節税効果が見込むことができます。
また、銀行からの借入等のマイナスの財産がある場合には、土地・建物・現金などのプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた上で、相続税が計算されるため、マイナスの財産があれば相続税を圧縮することが出来ます。
したがって、このようなマイナスの財産による節税効果も図れるため、銀行からの借入れと都心部の一等地の不動産(典型例はタワーマンション)を組み合わせた相続税対策(節税策)が流行りました。
本件においても、同様に節税効果が見込まれる事案でした。
(4)(3)のような節税対策について、従前の裁判例・裁決例において例外ルールが適用された事例―相続税対策(節税策)のみを目的としたと評価されるような場合
(3)で述べたような相続税対策(節税策)は、このような対策を取らなかった者と比較して、課税額に大きな開きが生じますので、このような相続税対策(節税策)のみを目的としているような事案については、従前の裁判例や裁決例は、例外ルールの適用を認め、このような相続税対策(節税策)を否定してきました。
具体的には、故人(被相続人)が亡くなる直前(相続開始前)に、不動産を購入し、故人がなくなった日(相続開始時)から間もなく当該不動産を売却したようなケースです。
(平成23年7月1日裁決・東京高裁平成5年1月16日税資194号75頁。
なお前者は、故人他界(相続開始)の前月に不動産購入し、故人他界(相続開始)後の10か月後に売却したケースです。また、後者は、故人他界(相続開始)の2月前に不動産購入・借入れを行い、故人他界後(相続開始後)の翌月に売却したケースです。)。
このようなケースは、不動産購入のための借入金の利息が当該不動産の賃貸収入よりも多額であるなど不動産活用による経済効果が見込めなかったり(東京高裁平成5年1月16日税資194号75頁)、相続人が当時、判断能力を欠いていた故人(被相続人)の名義を無断で使用し、不動産を購入していた(平成23年7月1日裁決)など、不動産購入の意図が相続対策目的のみであったと評価すべき事案でした。
こうした従前の裁判例に照らすと、本件類似の相続税対策(節税策)に例外ルールが適用されるためには、少なくとも、「①相続開始直前に不動産を購入+②相続開始後間も無く売却」といった2要件が要求されるという考え方もあり得ます。
また、当該不動産購入が相続税対策のみを意図してなされていたというために、上記の①②のプラスアルファの事情として又は➀②の事情が不十分な場合にこれを補う事情として、相続人が当時、判断能力を欠いていた故人(被相続人)に無断で故人の名義で不動産を購入した(平成23年7月1日裁決)とか、購入した不動産を経済的に有用に活用できていないまま、相続開始後の売却代金により借入金を返済した(東京高裁平成5年1月16日税資194号75頁)とか、故人(被相続人)の健康状態がかなり悪化し間近い時期のうちに相続が発生する可能性が高まってから不動産購入が駆け込み的になされていた(東京地裁判決令和2年11月12日)などという事情を要求する考え方もあり得るところです。
(5)本判決の事案及び判決理由から見る本判決の考え方
ア 本判決の事案
本判決の事案を、従前の裁判例・裁決例の事案と比較した際、以下の違いがあります。
2(1)及び(2)にて前述の通り、甲不動産の購入は故人(被相続人)の他界(相続開始時)から約3年半であり、乙不動産の購入は約2年半前であり、故人が他界する(相続開始)直前の購入ではありませんでした。
また、乙不動産については故人(被相続人)の他界後(相続開始後)、9か月後に売却しているものの、甲不動産については売却がなされていない事案でした。
もっとも、甲不動産及び乙不動産の購入の際の借入れの際に銀行が作成した貸出稟議書にはいずれも「相続税軽減目的の不動産購入のための借入」である旨、伺われる記載がなされていました。
イ 本判決の判決理由
本判決は、以下の判決理由により、例外ルールの適用を認め、路線価等ではなく時価(取引価格)により相続税を算定するとして、課税庁側を勝訴させました。
「これを本件各不動産についてみると、本件各通達評価額と本件各鑑定評価額との間には大きなかい離があるということができるものの、このことをもって上記事情があるということはできない。
もっとも、本件購入・借入れが行われなければ本件相続に係る課税価格の合計額は6億円を超えるものであったにもかかわらず、これが行われたことにより、本件各不動産の価額を評価通達の定める方法により評価すると、課税価格の合計額は2826万1000円にとどまり、基礎控除の結果、相続税の総額が0円になるというのであるから、上告人らの相続税の負担は著しく軽減されることになるというべきである。
そして、被相続人及び上告人らは、本件購入・借入れが近い将来発生することが予想される被相続人からの相続において上告人らの相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知り、かつ、これを期待して、あえて本件購入・借入れを企画して実行したというのであるから、租税負担の軽減をも意図してこれを行ったものといえる。
そうすると、本件各不動産の価額について評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことは、本件購入・借入れのような行為をせず、又はすることのできない他の納税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するというべきであるから、上記事情があるものということができる。」(最判令和4年4月19日判決)
ウ 本判決の事案及び判決理由から見る本判決の考え方~より柔軟な判断
まず、本判決は、購入した不動産の時価(取引価格)と路線価等との間に著しい価格差があることのみでは、例外ルールの適用はなされず、なお路線価等によるものとしています。
もっとも、このような価格差を積極的に利用し、相続税の減額を図ろうとしている場合には、例外ルールの適用をし、路線価等ではなく時価(取引価格)により相続税を算定する旨、述べています。
従前の裁判例・裁決例の考え方との違いは、以下の2つです。
まず、1つ目として、本判決は、従前の裁判例・裁決例から導き出される、「①相続開始直前に不動産を購入+②相続開始後間も無く売却」といった要件では判断していません。
もし、①+②の要件で判断されるならば、少なくとも、甲不動産については例外ルールの適用がなされず、部分的には、共同相続人(納税者)側が勝訴していたはずだからです。
また、2つ目として、相続税対策のみを目的としていた場合に限られる、といった厳格な考え方もなされていないと考えられます。
なぜなら、もし、本判決がそのような考え方に基づくのであれば、甲不動産及び乙不動産の利活用の状況等他の購入目的の存在や、購入時期付近における故人(被相続人)の健康状態の重篤化など相続税対策目的のみの購入であったことを支える事情についても挙げたした上で、およそ相続税対策のみを目的としている旨、述べるのが自然ですが、本判決はそのような説明をしておらず、「租税負担の軽減をも意図して」いれば十分である旨述べ、他の購入目的の存在を排除しない表現をとっているためです。
従前の裁判例・裁決例とは異なり、本判決は、より実質的かつ柔軟に判断し、例外ルールの適用を認めているものと評価できます。
すなわち、本判決は、まず、「本件購入・借入れが行われなければ本件相続に係る課税価格の合計額は6億円を超えるものであったにもかかわらず、これが行われたことにより、本件各不動産の価額を評価通達の定める方法により評価すると、課税価格の合計額は2826万1000円にとどまり、基礎控除の結果、相続税の総額が0円になる」という著しい節税(減税)効果があることを挙げています。
その上で、かかる節税(減税)効果について、「相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知り、かつ、これを期待して、あえて本件購入・借入れを企画して実行した」ものとして、節税(減税)効果に関する故人(被相続人)や共同相続人(納税者)の積極的な利用意図を挙げ、例外ルールの適用を認めています。
要するに、本判決は、A著しい節税(減税)効果+B被相続人・相続人の積極的な利用意図の2点を要件として、例外ルールの適用を認める考え方をしていると評価できます。
また、Bについては、本判決が「相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知り、かつ、これを期待して、あえて本件購入・借入れを企画して実行した」というように、故人(被相続人)及び相続人(納税者)の主観を特に重視していることから、B―1.著しい節税(減税)効果を伴う不動産購入を、相続開始の直前とまではいえないにしても相続開始に近い時期に行ったことという客観的・外形的事情のみならず、B-2.借入れの際に銀行が作成した貸出稟議書に相続税対策のための購入である旨、記載されていたという事情も故人(被相続人)及び相続人(納税者)の主観を推認する事情として、判断に影響を及ぼしていると推察されます。このように、本判決は、要件の明確性よりも課税の公平性の担保という実質面を重視し、柔軟な基準により判断したものと評価できます。
(6)本判決が相続税対策(節税策)に与える影響
前述の通り、本判決は、例外ルールの適用がなされ、要件の明確性よりも実質面を重視し、柔軟な基準により判断したものです。
もっとも、故人(被相続人)及び相続人(納税者)側から見れば、相続税対策(節税策)のみを目的としているような極端に露骨なケースでなくとも、結果として、かなりの節税効果があり、かつ、節税目的をも肯定されてしまうような事情があれば、本判決の基準によれば、時価(取引価格)による課税を受けるリスクが付きまといます。
また、どのような場合であれば、時価(取引価格)に基づく相続税が課されるという不利益を被るのかが不明瞭となってしまうという面もあります。
例えば、どの程度の節税効果があれば要件A(大幅な節税効果)を満たすこととされるのか、また、節税の意図が多少でも肯定されるような状況であれば要件B(節税効果の積極的な利用意図)を満たすのか、そうでなくとも節税目的と節税以外の目的とが半々程度であれば要件Bを満たすのか、節税目的が節税以外の目的を上回っていなければ要件Bを満たさないのか、そして、具体的に相続開始の何年前に購入し、期間・利用運用実績においてどの程度の利活用があれば、要件Bを否定できる程度に節税目的を薄めることができるのか、といった微妙な判断が要求されます。
こうしたことから、本判決の登場により、不動産購入(特に、不動産の購入と同時に借入れも行う方法)による相続税対策(節税策)については慎重にならざるを得ません。
例えば、まず、故人(被相続人)自身の健康状態などから、そう遠くない時期に相続開始が予想される場合は、本判決を踏まえると、時期的に相続税対策を積極的に意図したものと評価される虞があることから(Bが肯定されるリスクがあります)、リスクをより排除するという考え方を採るのであれば(Aが肯定されてしまうような)大幅な減税効果を伴う不動産購入は控えた方が良いということになります。
また、大幅な節税効果が予見される不動産購入を行う場合(Aが肯定されるような場合)は、(Bが肯定されてしまうリスクを可及的に回避するため)減税効果は、長期的な利用・運用と共に実現できるよう、早期の段階から慎重に準備しておく必要があります。
また、万全を期すならば、大幅な節税にならないよう、かつ、かなり早期の段階から不動産を購入(AもBも否定できるようにしておく)しておく必要があります
加えて、万が一、故人(被相続人)が予想外に早く亡くなられてしまい、外形的には短期間のうちに大幅な節税を図っているように見えてしまうとき(要件AもBも肯定されてしまうようなとき)に備え、購入当時、専ら居住・事業目的や長期的運用目的のみを意図しており相続税対策(節税策)としての意図は有していなかったことを後日証明できるような証拠を残しておく等、予想外の課税リスクをできうる限り低減していくことが求められます。
なお、不動産購入による節税については、上記の対策を施したとしても課税リスクは残りますので、そもそも、課税の公平性を害さないような別の方法を考える必要があることにご留意ください。
投稿者プロフィール

- 代表弁護士
-
新宿を拠点として、相続案件に多数取り組んでいます。
他士業と連携し、スムーズな解決に尽力いたします。
最新の投稿
 記事2023年12月27日寄与分とは?-寄与分の分類や貰えるためのポイントなど詳しく解説します。
記事2023年12月27日寄与分とは?-寄与分の分類や貰えるためのポイントなど詳しく解説します。 記事2023年8月4日代襲相続とは?‐発生する条件や代襲相続人の範囲、割合など詳しく解説します。
記事2023年8月4日代襲相続とは?‐発生する条件や代襲相続人の範囲、割合など詳しく解説します。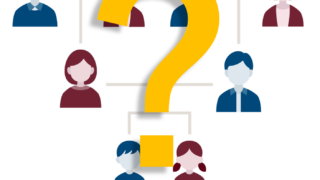 記事2023年8月4日法定相続人とは?相続人の順位と割合をわかりやすく解説します!
記事2023年8月4日法定相続人とは?相続人の順位と割合をわかりやすく解説します! 記事2023年7月10日遺留分とは?‐遺留分をもらえる人や計算方法など、わかりやすく解説します
記事2023年7月10日遺留分とは?‐遺留分をもらえる人や計算方法など、わかりやすく解説します
