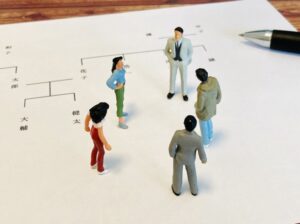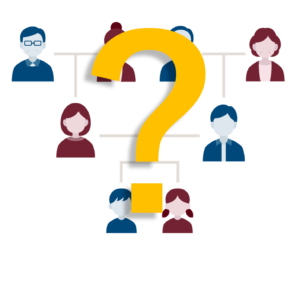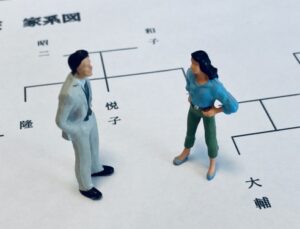寄与分とは?-寄与分の分類や貰えるためのポイントなど詳しく解説します。
「事業を手伝っていたのにこの配分はおかしい!」「両親と同居をして面倒をみていたのに何もないのは納得がいかない・・・」 相続では、亡くなったかた(被相続人)が残した遺産が相続人に引き継がれることになりますが、相続人の中に特 […]
代襲相続とは?‐発生する条件や代襲相続人の範囲、割合など詳しく解説します。
高齢化が叫ばれる昨今、親より子が先に亡くなることも珍しいケースとは言えなくなってきています。代襲相続とは、本来であれば相続人(財産を受け継ぐ人)になるはずの人が、被相続人(故人)より先に亡くなっている場合、その人の子や甥 […]
法定相続人とは?相続人の順位と割合をわかりやすく解説します!
人が亡くなると、その亡くなった方(被相続人)の財産を引き継ぐ相続が発生します。遺言書がある場合を除き、親族の誰かが遺産を受け継ぐこととなりますが、それが法定相続人です。この記事では、法定相続人には誰がなり、どれくらいの割 […]
遺留分とは?‐遺留分をもらえる人や計算方法など、わかりやすく解説します
遺言書があったが、「財産のすべてを長男に譲る」といった不公平な内容だった! 遺言通りに財産を分けたが、実はほかの兄弟に多額の生前贈与をしていた! 財産の大小に関わらず相続トラブルは後を絶たず、上記のように遺言により争いが […]
遺言書って必要?何を書くの?揉めないためのポイントを押さえましょう!
「うちは大した資産もないし、揉めることも無いわ」「遺言書なんて大げさよ…」多くの一般の方はこのように思われるのではないでしょうか。しかし、相続トラブルの約3割が、遺産額1,000万円以下のケースで発生しています。そして特 […]
遺言書は3種類!それぞれの特徴を弁護士が解説します。
遺言書には「普通方式遺言」と「特別方式遺言」の2種類がありますが、一般的に用いられるのは普通方式遺言です。普通方式遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。この記事では、それぞれの遺言 […]
【2023年4月施行】民法改正で相続はどう変わるか?詳しく解説します!
2023年4月以降に順次施行される改正法では、民法や不動産登記法などの法律に変更が加えられます。遺産分割に10年の期限が設けられたり、不動産登記が義務化されたりするなど、相続に関する取扱いも一部変更がありますので、この記 […]
遺産の範囲・評価に関する認識のズレによる遺産分割協議におけるリスク
目次 第1 遺産の範囲や評価に関し勘違いをしたまま遺産分割協議書を締結してしまった場合における遺産分割協議の効力 第2 遺産分割協議で後でもめないための方策 第3 相続不動産・株式について認識のズレ(遺産分割協議無効リス […]
代襲相続と養子縁組のタイミング
故人よりも先に亡くなっている養子がおり、その養子に子がいた場合、養子の子が代襲相続人になれるかどうかは、養子縁組をしたタイミングと養子に子が生まれたタイミングによって異なるため注意が必要です。具体的には、まず、養子の子が […]