遺留分を侵害する遺言書がある場合、当該遺言を無効にすることが遺留分を侵害された相続人によって最善の道であり、この意味で、遺留分侵害額請求は次善策です。
なお、遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人(故人の配偶者・子・親などの直系尊属(これらの者の代襲者を含みます))が、遺言内容に関わらず最低限保証される、遺産全体の価額に対して割合的に有する金銭的請求権です。(民法1042条)
(上記の遺留分の割合は、相続人各自の有する法定相続分の2分の1または3分の1となります(民法1042条第1項1号・2号))
しかしながら、遺言の無効を確信している場合であっても、(遺言の無効を争うことを留保しつつも、遺言の有効を前提とした)遺留分侵害額請求(の意思表示)は一応行っておくべきです。
なぜなら、遺言の有効無効を最終的に判断するのは裁判所であり、裁判には時間がかかります。
他方で、遺留分侵害額請求には相続開始を知った時から1年以内という短期間の行使期限があります(民法1048前段)。
したがって、裁判で争っている間に、遺留分侵害額請求の行使期限を過ぎてしまい、最終的に裁判でも敗訴してしまった場合は、何も得られなくなってしまいかねません。
これに対し、遺留分侵害額請求をひとまず行使しておけば、期限は10年間に伸びます(民法166条1項)。
よって、相続開始後、自身の遺留分を侵害する遺言書が発見された場合は、遺言の有効性を争うことを留保しつつも「念のため」遺留分侵害額請求も行っておくべきでしょう。
また、内容証明郵便による方法など、期間内に遺留分侵害額請求を行ったことを後日証明できるような方法を選択すべきです。
投稿者プロフィール

- 代表弁護士
-
新宿を拠点として、相続案件に多数取り組んでいます。
他士業と連携し、スムーズな解決に尽力いたします。
最新の投稿
 記事2023年12月27日寄与分とは?-寄与分の分類や貰えるためのポイントなど詳しく解説します。
記事2023年12月27日寄与分とは?-寄与分の分類や貰えるためのポイントなど詳しく解説します。 記事2023年8月4日代襲相続とは?‐発生する条件や代襲相続人の範囲、割合など詳しく解説します。
記事2023年8月4日代襲相続とは?‐発生する条件や代襲相続人の範囲、割合など詳しく解説します。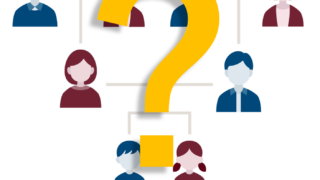 記事2023年8月4日法定相続人とは?相続人の順位と割合をわかりやすく解説します!
記事2023年8月4日法定相続人とは?相続人の順位と割合をわかりやすく解説します! 記事2023年7月10日遺留分とは?‐遺留分をもらえる人や計算方法など、わかりやすく解説します
記事2023年7月10日遺留分とは?‐遺留分をもらえる人や計算方法など、わかりやすく解説します
